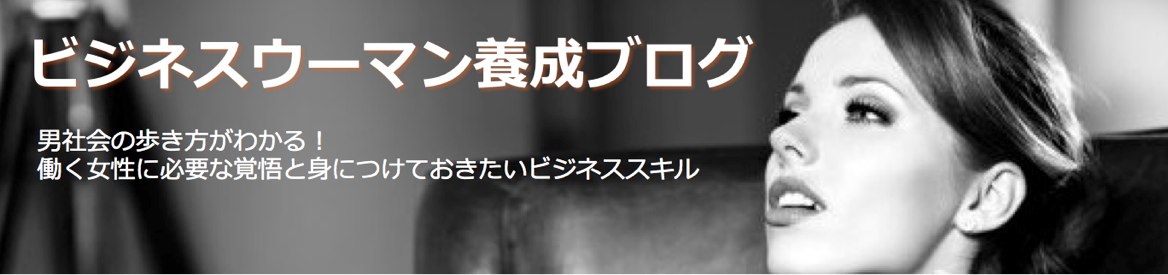なぜキャッシュレス決済は災害に弱いのか?停電時の課題と対策

日本は東日本大震災以降、熊本地震や各地で起きる集中豪雨、北海道地震など自然災害が相次いでいます。
実は私も被災したことがあり、災害が起きると大変な状況になる・・・ということは身を持って経験しています。
そんな中、被災生活を振り返ってみると「地震」そのものと同じくらい、インパクトがあったのは「断水」と「停電」です。
インフラは非常に重要で、これら無くして生活は成り立たないと思いました。
どうにか地震の揺れが落ち着いて、食料を買いに出た時、外ではこんなことが起きていました。
・お店がほとんど空いていない
・レジが使えず手計算で奮闘している従業員の姿
・「クレカ利用できません」の貼り紙の文字
・ATMではすぐに現金を引き出せない
物を買うのも大変な私たち。お店の人たちもレジなどとても大変そうだったのを覚えています。
では、こういった時に今注目が集まっているキャッシュレス決済はどうなるのかが気になりませんか?
「災害時には不便だった」「使えなかった」という意見が多く、「ほら、やっぱり。キャッシュレスはダメじゃん!」とその脆弱性を指摘する声も。
しかし、それだけを理由にキャッシュレス決済そのものを否定するのは少し無理があるのです。
確かに電気が途絶えた時は、今のところキャッシュレス決済は不利な面もありますが、災害時には現金でも問題点があったりしますからね。
それらを踏まえて、今回は災害が起きた時のお金周りのことを一緒に考えていきましょう!
今のうちから考えておくことで、万が一の時も冷静な判断ができるはずです。
なぜキャッシュレス決済は災害に弱いのか?停電時の課題と対策
なぜ停電するとキャッシュレス決済の機能が使えなくなるのか?

電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済では、電力とインターネット回線が必要です。
停電により、これらが止まってしまうとカードの情報を読み取る端末などが作動しなくなり、情報を共有しているネットワークにもアクセス出来なくなるので、キャッシュレス決済の機能が全く使えなくなってしまいます。
停電時に使えなくなるキャッシュレスサービス

交通機関のICカード
ホストコンピューターとの接続が切れて、ネットワークにアクセスできない状態となるので、交通機関のICカードは停電時に利用できなくなります。
電子マネーの決済
電子マネーは停電が起きると使えなくなります。北海道地震の際、他の店舗が営業を続けられない中、セイコーマートだけが奮闘していました。
セイコーマートは、ネットがなくてもオフラインでも決済ができるサービスと非常用電源などを活用してレジを動かしていたそうですが、このサービスを使っても「電子マネーは利用できなかった」そうなので、災害時には電子マネーは使えないと覚えておきましょう。
公共料金の支払い
コンビニなどのレジは停電が起きても、無停電装置が設置されているので、停電が起きても何時間かは乗り切ることができるとのこと。
しかし、これがダウンしてしまうとレジも使えなくなり、公共料金の支払いや宅急便の受付などは全く使えなくなります。
復旧の見通しがない状態では受け付けても、その後の処理ができないので災害後すぐに公共料金の支払いがストップするお店が多いことも知っておくといいでしょう。
− − − − −
現金主義はもう通用しない!?
進化する「キャッシュレスサービス」に関する記事をまとめました。
停電になってもキャッシュレス決済ができるようにする対策は?

オフライン対応ができるサービスの普及
災害時にキャッシュレス決済ができなくなってしまうのは、電力とネット回線がダメになってしまうから。オフラインでも対応出来るサービスが今後普及していけば、「災害時にキャッシュレス決済は使えない・・・」ということにはならないはずです。
どんな状況にも対応できるようにリスク分散
決済方法が色々とある中、「自分はこれしか使わない!」と決めてしまうのは危険なことです。
特に現金主義の人に多いのですが、災害時に現金の管理や持ち出しは難しいです。タンス預金をしていた人では、津波や浸水でほとんどの現金を失った・・・という話も。
それに避難所背の生活など、みんなが苦しくて極限状態で生活していると、現金の盗難なども起きやすくなります。
そう考えると「50%現金」「50%キャッシュレス」というように、所持金を分散しておくと安心です。
店舗は大型POSレジではなく、省電力なiPadレジアプリを
災害時には電力を必要最小限に抑えたいところ。キャッシュレス決済に使うiPadレジは、大型のPOSレジと比べても電力は少ないので災害時には有利です。
お店側も利便性の向上と災害時のリスク回避のために、キャッシュレス化を進めておく必要があると考えます。
Squareならオフラインでもクレジット決済は可能
北海道地震の際に奮闘していたセイコーマートの例をあげましたが、TwitterのCEOジャック・ドーシーが創業したSquare社のサービス『Square』を導入していました。
このサービスを使うと、オフラインでもクレジットカード決済が可能になるで災害時にも有利です。
しかし、クレジットカードは使えるけれど、電子マネーは利用できなかったり、偽装カードの検証ができないなどの問題点も。
「これが完璧なサービスだ!」とは言い切れない部分もありますが、今後類似のサービスが増えていくことを期待しています。
災害時に活躍するインプリンター
インプリンターとはネット回線がない場所でもクレジットカード決済を行える小型器具のこと。

クレジットカードの表面にあるエンボス加工を読み取って、カード番号などを複写できるのが特徴です。
最近はあまり見かけませんが、災害をきっかけに再びその価値が見直されています。
今日のまとめ
なぜキャッシュレス決済は災害に弱いのか?停電時の課題と対策
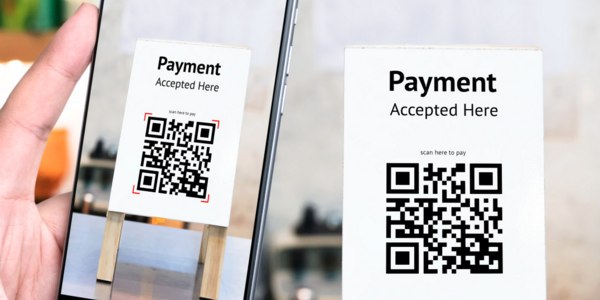
停電には大きく分けて2パターンあります。
①停電のみ(通信ネットワークは活きている)
②通信ネットワークにも障害が生じている
②の場合は「現金払い」しか方法はなく、お店側は手計算で対応するしかありません。
小銭不足などの問題は起きていますが、スタッフさんも被災して大変な時に対応をしてくれているので、少しばかり不便でも仕方ありませんね。
それから①の場合は、災害時にもキャッシュレス決済できるインフラの整備が整ってくると悩みも解消されることでしょう。
決済方法が多様化している現代社会。
様々なシーンを想定しながら、キャッシュレス生活にも早い段階で慣れておきましょう!
◉ なぜ停電するとキャッシュレス決済の機能が使えなくなるのか?
・電力とインターネット回線が使えないと、カード情報を読み取る端末などが作動しなくなるから
◉ 停電時に使えなくなるキャッシュレスサービス
・交通機関のICカード
・電子マネーの決済
・公共料金の支払い
◉ 停電になってもキャッシュレス決済ができるようにする対策は?
・オフライン対応ができるサービスの普及
・どんな状況にも対応できるように所持金を分散しておくと安心
・店舗は大型POSレジではなく、省電力なiPadレジアプリを
・Squareならオフラインでもクレジット決済は可能
・災害時に活躍するインプリンター
− − − − −
いつ来るかわからない地震や暴風雨への対策はできてますか?
あなたにオススメの記事
当サイトへのご訪問ありがとうございます。記事のご愛読に感謝します。